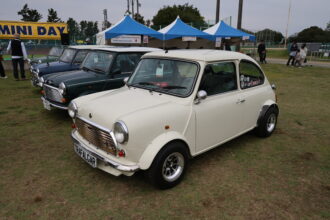1964年、ミニに初めて大掛かりな変更が行われることになる。前述の4速ATの追加に加え、足回りにも大きな変更が加えられるのだった。
ミニをシンプルで素朴なクルマとしていたイシゴニスは、高価で贅沢な装備をミニに与えることは大嫌いだった。そのため、ミニのマイナーチェンジについても難色を示したと言われている。
しかし友人のエンジニア、アレックス・モールトンと共同開発していたサスペンション機構、ハイドロラスティックだけは別だった。実はミニには当初からこのサスペンションを採用する計画であったが、なかなか納得のいく出来栄えにならなかったのだ。
ハイドロラスティックは、サスペンションスプリングをゴムと液体で構成し、前後の液体をパイプで連結して液体の圧力を伝達させる。これにより前輪が路面から衝撃を受けた時、後輪へと衝撃力を受け流すだけでなく、後輪を上下させる作用が働くことで、フラットな姿勢を保つのだ。
ようやく完成したハイドロラスティックサスペンションをミニに採用したのは64年のことだ。
ハイドラスティックサスペンション自体は、素晴らしい乗り心地を実現するものであった。サスペンションストロークも本来の設計通り豊かなものとなり、当時から「魔法の絨毯」と呼ばれるほど、ミニの乗り心地を激変させた。

同じくモールトンの特許技術によるラバーコーン・サスペンションも、しなやかでミニらしい乗り味を見せてくれるが、ハイドロラスティックはそれとは全然違う、柔らかいけれども安定感のあるフラットな乗り味が特徴的だった。
しかもクーパーSが開発され、モータースポーツにも積極的に参加していたBMCは、クーパーとクーパーSにはハイドロラスティックサスペンションを標準装備とするだけでなく、よりスポーティな走行に適した、踏ん張りの利く仕様もオプションで用意したのだ。それはスプリングとなるディスプレッサーから伸びるホースに記されたバンドの色で識別できるようになっていた。
しかしクーパーSは高性能ではあるが豪華仕様でもあったため、スポーティに仕立てられたとはいえ限界域での挙動は、いささか柔らかすぎた。66年には標準仕様のハイドロラスティックも強化品に変更されたが、街乗りでの使用も考えると限度があった。

当時英国や日本ではクーパーSがラリーやサーキットで活躍していたが、その挙動の不安定さはドライバー泣かせとも言えた。逆に言えば、挙動変化の大きいハイドロラスティックサスを制して、際立つ速さを魅せたドライバーは、本当に超絶テクニックと度胸の持ち主であった、ということになる。
65年にはミニのプラットフォームを利用したオフロードカー、ミニモークも発売された。このミニモーク、そもそも英国の軍用車両への採用を目指して開発されたが、肝心のオフロード性能はそれほど高くなかったことから採用が見送られ、市販化されることになったモデルである。

軍用として開発されたため、航空機で運びパラシュートで降下させることを考慮しており、フロントウインドウを畳めば積み重ねて収納できるなど、スペース効率にも優れたアイデアが盛り込まれていた。
1966年には、ミニのドアのアウターハンドルの形状が改められ、ドアハンドルの先端に服などが引っかからないようドア側に突起が設けられた。